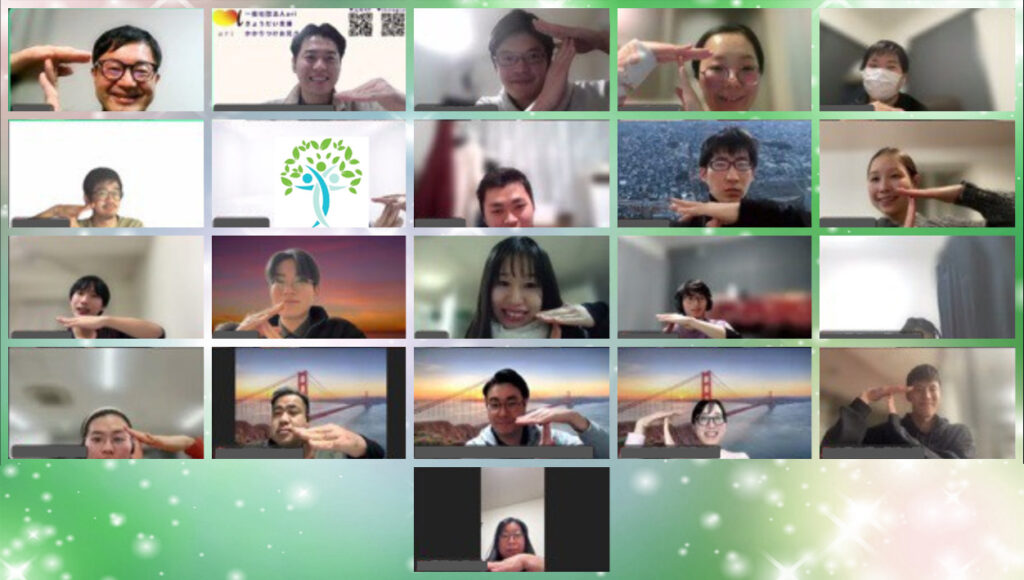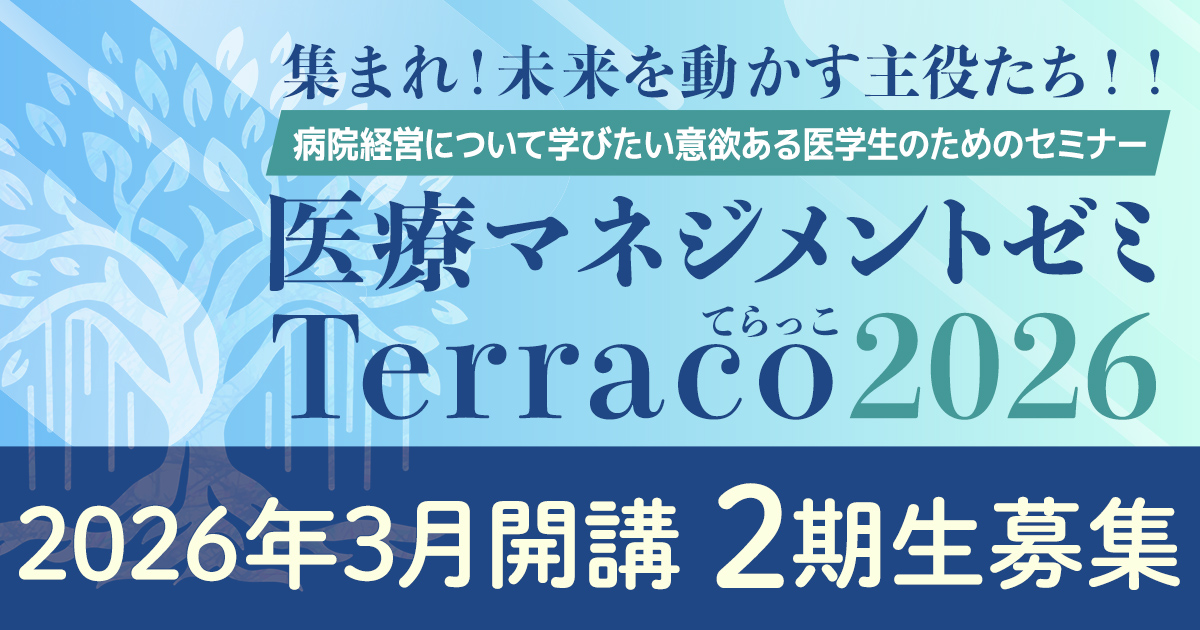〈第1回〉リーダーシップ
ひとがひとを管理する~マネジメント・リーダーシップの難しさ~
【講師】石井 仁
自身がリーダー経験でとても悩んでいる時期だったのでとてもタイムリーに、痒いところに手が届くような時間でした。
教育のお話がとても興味深かったです。後輩を育てるためには、自分が仕事を奪わず、見守ることが大切だと学べました。今回の講義を活かして、将来は周りへの感謝や配慮を忘れず、目的・目標を共有して活動を進められるリーダーになりたいです。
リーダーシップには、「後人を育てる」という人材育成が大切で、その結果として、有事の時に、誰もがリーダーシップ・マネジメントが出来る状態をつくっておくことが理想だというお話を伺い、今までの自分に足りなかった部分はここだったのだと気付かされました。
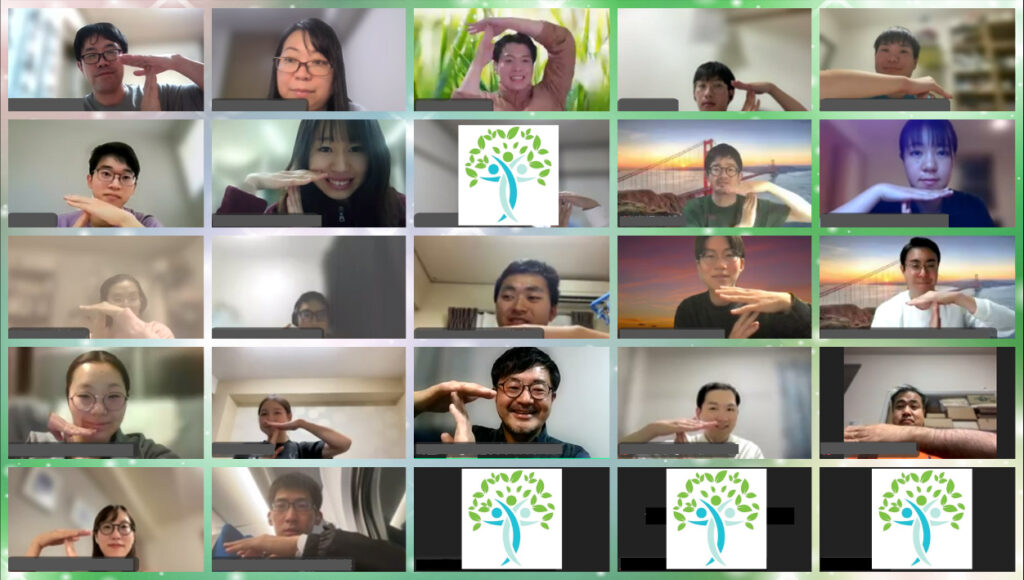
〈第2回〉コミュニティホスピタル
若手医師が選んだ総合診療と中小病院というキャリアの選択
【講師】近藤 敬太
「中小病院がコミュニティホスピタルとしてなぜ機能できるのか」を理解できました。また、医療者視点、病院経営視点の両方の視点が入っていた点がとても面白かったです。さらに、個人の生い立ちやモチベーションについて具体的に教えていただき、自分の将来をどうしたいかを本気で考えるきっかけになりました。
行動規範や総合診療への想いを具体的に聞くことができた上、コミュニティホスピタルの概念理解および議論の射程を把握することができたので、非常に勉強になりました。活気付いてはきているものの、九州はいまだに医療過疎地域が多いため、総合診療をインフラ化する発想を行政機関とも共有しながら、安心して生活できる街づくりに貢献できたらと思いました。
初期研修の選び方やその先のキャリアの進み方のお話が印象的でした。私は将来結婚して子どもを育てたいと思っているので、育児の時間が増えるとますます医師として働く時間は短くなると思います。将来的に地域医療に携わりたいと思っていますが、「都市部の大きな病院で症例を経験してから地域に出るのが普通なのでは」と先輩に言われてから、そのようなキャリアを考えていました。しかし、今回の講義を聞いて、時間は限られているので、最初から自分のやりたいことをすべきだと考えるようになれました。時間の使い方、やりたいことの優先順位について考える貴重な機会でした。
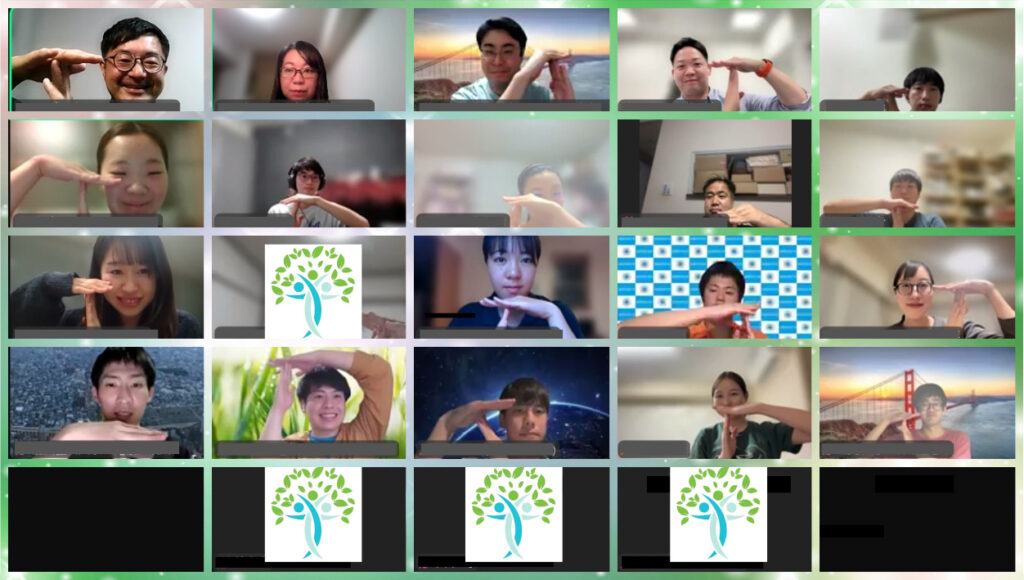
〈第3回〉医療DX
医療DX ~ 現在地点と社会実装
【講師】小西 竜太
医療DXの全体像とトランスフォーメーションの重要性を理解できました。実務家ならではの現場の苦労も感じました。また、キャリアの話がとても面白かったので、ぜひその部分ももっと深掘りいただけたらと感じました。
想像がつくことは何でもできるであろう「D」の部分とそれを実際に入れて変革していく「X」の部分と、とても理解が進みました。また、スプレッドシートへのリアルタイムでの書き込みは順番に聴講生が話すよりも同時に多くの意見をみることができ、とても良かったです。
トランスフォーメンションのイメージを具体的に持つことができました。「その先に何が待っているのか」、「次のパラダイスシフトは何なのか」を想像してみましたが、まだ答えは分かりません。臨床力を前提として、「異なる分野にアンテナを張る」、「未知のことを想像する」、「俯瞰的に考える」ことの大切さも認識できました。
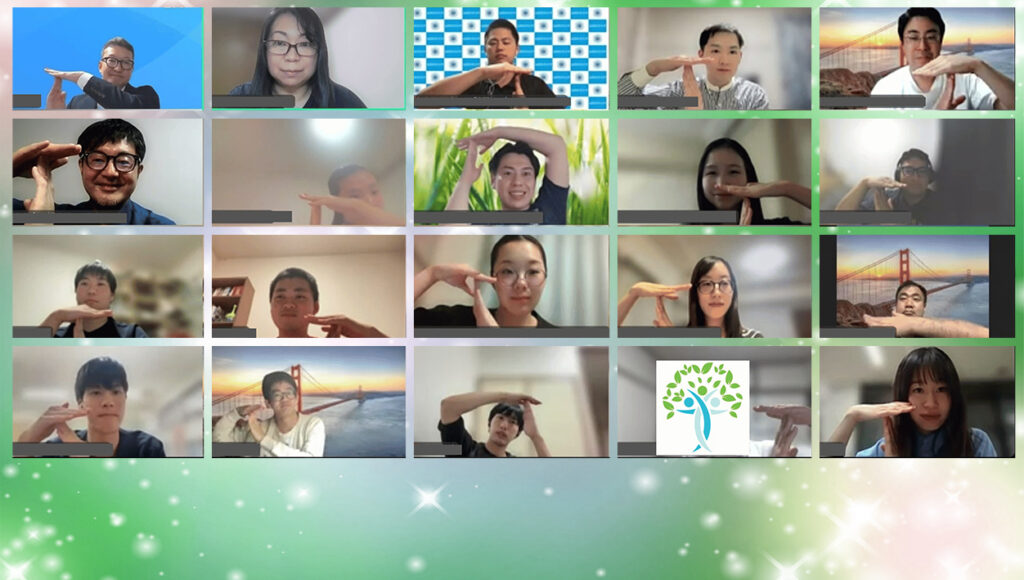
〈第4回〉人材・組織開発
“現場発”の人材開発 —医療人・組織人としての成長を支援する—
【講師】西川 泰弘
事務職の方の人材開発について知らないことが多く、非常に新鮮でした。学会発表などを推奨することで組織内での学びの蓄積や成長の実感が得られるのは非常に良いアプローチだと感じました。また、参考文献一覧を提示いただいたのも今後の学習の参考になるのでとても有用だと思いました。
前半パートでは、病院の人事とは何かを具体性を持って理解できたことが良かったです。後半パートでは初期研修に向けた心構えを考えるヒントになりました。また、もし可能であれば、病院の人事評価や人材育成の中で特に苦労したこと・失敗したこと・軋轢など、「ヒト対ヒトのリアルな話」も聴けたら、受講生としてより学びが深まると思いました。
人材開発の理論と病院における具体的な取り組みについて、これまでのご経験やお考えを踏まえたリアルなお話を伺うことができ、大変勉強になりました。事前資料を活用した講義中のやり取りや、「講義」と「インタビュー」の二部構成など、研修・教育に携わっていらっしゃるからこその工夫が随所に見られ、人に教える方法を考える上でも非常に参考になりました。
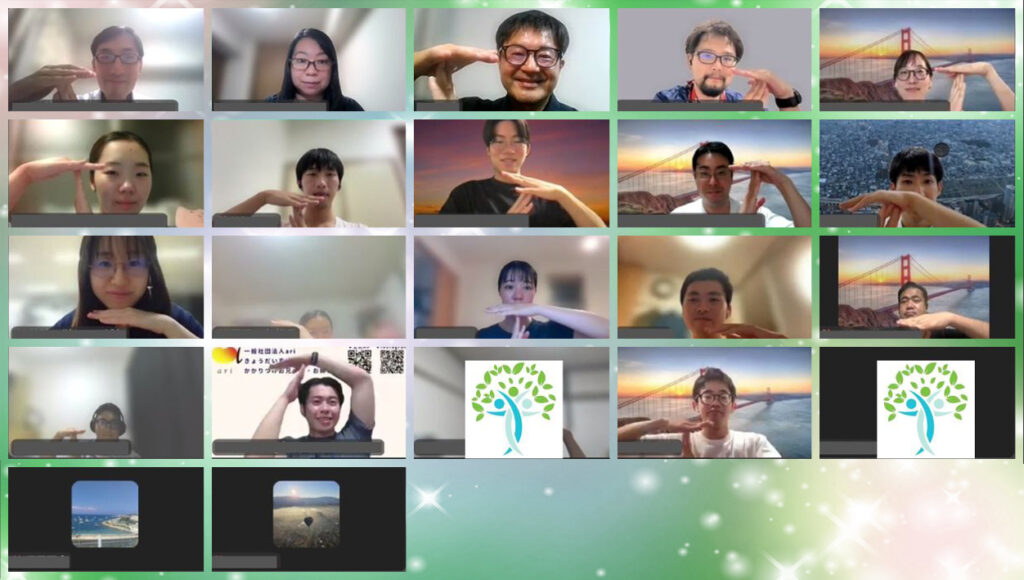
〈第5回〉まちづくり・ポジショニング
なぜ、まちづくりが競争優位になるのか
【講師】藤井 将志
病院がまちづくりをする必要があるのかというテーマは非常に興味があったため、今回の講義をとても楽しみにしておりました。藤井さんなりの理由や、他の学生の意見も交えて自分も深く考えることができたので、とても有意義な時間になりました。一方、地域づくりの事例の多くに「自分が実際に行動する際にどう落とし込めばいいのか分からない」とも感じました。事例のみならず、1つ1つのプロセスも知ってみたいです。
非常に多様でたくさんの取り組みをなさっていて驚きました。病院に実際に足を運んでみたいと思いました。自分自身、様々な地域活動に取り組みながらも、その意味付けや価値の捉え方に自信を無くしていたところでした。しかし、今日の講義を通して、「楽しそうな背中を見せる人間は魅力的に映る」こと、「活動を周りで見てくれている人々との関わりが何よりも大きな財産となる」こと、そして「研究などを通してその価値を証明することが活動を継続するための自信や資源につながる」ことを学び、明るい気持ちになれました。
まちづくりの楽しさを感じられる講義でした。将来的に病院経営を一つの目標にしておりますが、その中で「街まで丸ごといろいろやってみよう」という藤井さんのお話がとても興味深く、驚きました。また、自分から全部の事業を積極的に始めた訳ではなく、「できたご縁から少しずつその縁を広げていき、話が大きくなっていった」というお話が印象的でした。
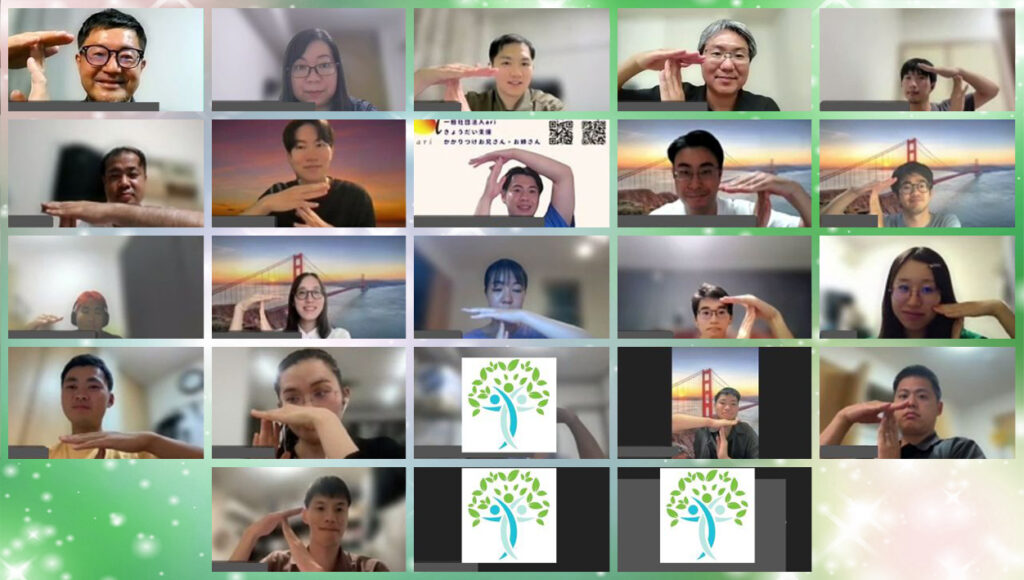
〈第6回〉災害医療・BCP
今 求められる災害医療について
【講師】久野 将宗
災害医療の基本的な考え方やその歴史的な変遷について学ぶことができ、個人としても、将来病院運営に携わる際にも大変参考になる内容でした。医療が日々進歩する中で、災害医療も災害の経験を重ねるごとに改善され、新たに生じる課題に対して行政を含め、多方面でシステマチックに取り組まれている点が特に印象的でした。
熊本地震についてのお話の中であったように、障害を持つ方など「普通に避難するのが難しい方に対する医療はどのようになっているのか?」が気になりました。また、将来 在宅医療に携わりたいと思っていることから、災害時、人工呼吸器がついてたり、自力では動けない患者さんの対応に際して、在宅医がどのように関わるのかも学びたいと思いました。さらに、「DMATなどで外部から入る医者がその地域で元々働く医師とどのように連携するのか?」も知りたいと思いました。
災害医療というと国試的にはトリアージの印象が強くて、それ以外のことはあまり考えてきませんでしたが、今回の講義を通じて考えなければならないことが山ほどあることを学びました。個人的に印象に残っているのは、地震の継続時間と被害規模の関係についてです。今回の学びを活かして、実際に災害が起きたとしたら冷静で的確な行動ができるようになりたいなと思いました。

〈第7回〉医療安全
医療安全(患者安全)について考えてみよう
【講師】平松 真理子
医療安全の講義は大学でもありましたが、正直よく分からずあまり真剣に聞いていませんでした。しかし、平松さんの講義にて実際の医療事故の事例や質問を提示してくださったことで、医療安全について自分ごととして考えることができました。インシデントレポートは小さなことでも書く習慣を身につけます。
医療安全について非常に分かりやすい講義をしていただきありがとうございました。チャットを使った双方向の進め方で話を聞きやすかったです。「医療事故の当事者はいい風に考えてしまうため、第三者を入れることが大切」ということが印象に残っています。また、今ほどワークライフバランスの認識がない頃、家庭も仕事もどっちも取ってこられた先生のキャリア像がとてもカッコいいと感じました。
とても密度が高い講義でした。これまで学校でも医療安全の講義は受けてきましたが、それら全てを統合し発展させたかのような内容でした。チャットで答える質問で皆さんの意見がたくさん聞けて楽しかったこと、具体的な事例を紹介いただいたことによりリアリティが増し集中力を切らさずに最後まで聴けたこと、内容→キャリアの順にすることで先生のキャリアについてより一層興味を持って伺えたこと、が特に良かったです。私はずっと臨床をしたいと思っていますが、最低10年というのも先生のキャリアからとても説得力のある数字でした。ありがとうございました。
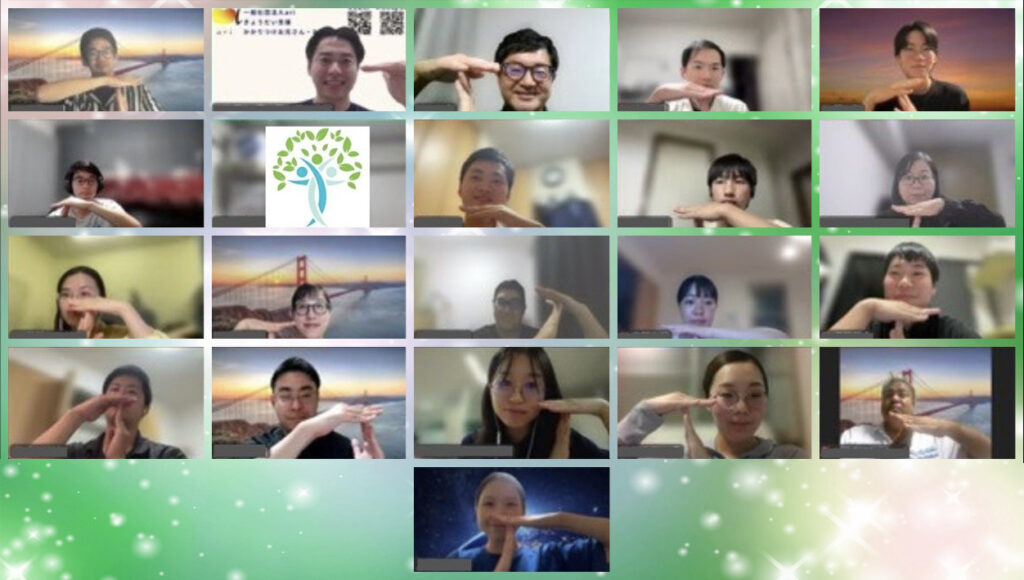
〈第8回〉病院広報・マーケティング
新時代の病院マーケティング戦略
【講師】松本 卓
広報・マーケティングは今回のプログラムの中でも特に聴きたい内容で、とても興味深い話を聞くことができました。その中でも、医師のメディア露出の話や、どうやって困った時に自分の病院を思い浮かべてもらうかなどの話が興味深かったです。情報を忘れていってしまう顧客に対して何度も何度も定期的にアプローチすることが大切だと感じました。
貴重なご講義をありがとうございました。非常に楽しい怒涛の2時間でした!「打席数と打率を稼ぐしかない」「ほんのちょっとのチリつも作戦」など印象的なフレーズが多様されており、記憶に焼き付いております。何より印象的だったのは、現状やそれそれのツールについてn数をきちんと確保した上での徹底的な分析でした。分析を行い、選任のディレクターを設置し、医師の露出を増やし、打席数と打率を稼いでいくという手法、非常に勉強になりました。医師個人のマーケティングやブランディングにも応用できそうだな、と思ってお聞きしておりました。また、ご教示いただける機会を楽しみにしております。ありがとうございました。
具体例を交えて話していただき、分かりやすかったです。経営する立場に回る前からも、日常的に取り入れることのできることが多いと感じました。自分の良さを知ってもらうためには、①たとえ、みんながしてることであってもアピールポイントにしてもいい(当たり前のことでもアピールポイントになる)、②〇〇できるといっても相手には実感が湧かないので具体的にみせる。あと、「自分の本分は病院の患者数を増やすことだからデザインなどの仕事は外部に任せている」も大事なことだと思いました。自分のすべきこと以外は周りに任せる潔さがあってこそ、自分のすべきことをしっかり果たせるのだなと思いました。これから、私も自分のすべきことは何かを忘れずに、それ以外のことはそれに特化した周りの人に頼れるように努力したいです。

〈第9回〉人材採用・ブランディング
9割の病院経営者が知らない 医師の正しい採用方法
〈講師〉紀平 浩幸
本当に密度が濃くて、講義だけで2時間欲しかったくらいです。PSRを書いたらキャッチコピーは生成AIに書いてもらえる、GAMMAでのサイトといったAIの活用方法も学べて嬉しかったです。ペルソナが大事だと講義だけで聞いただけでも興味深かったですが、ワークショップを通して、その大事さとその設定内容の大事さが分かった気がします。最近、様々な回のテラッコやスピンオフの内容が繋がってきて、さらに楽しくなってきました。ありがとうございます。
前回に引き続き、ブランディング関連のコンサルに携わっておられる方ならではの、分かりやすい講義で、その進め方からも多くを学ぶことができました。また、医局崩壊に伴う医師人材の流動化によって、人材派遣会社が医療業界に参入し、オルタナティブが少ない中で高い仲介手数料を求め、医療機関の財政を圧迫しているという問題について、今回初めて知りました。さらに、医師と医療機関の適切なマッチングや定着率向上の観点でも、待遇を重視し「数を打てば当たる」方式で紹介を行う現状の人材派遣会社の方針が、望ましくない影響を与えている点も興味深い内容でした。こういった現状に対する解決策としてPSR の考え方を医師採用にも取り入れ、病院ごとの特徴を明確にしながら、相性の良い人材に向けて尖ったアピールをしていくことの重要性も理解できました。医療過疎地域の医療体制を、行政や病院マネジメントの視点から良くしていきたいと考えている自分にとっても、地域ごとの強みや地域医療そのものの価値にしっかり目を向けることが大切だと改めて感じました。
地域医療枠という入学枠は人材紹介会社にお金を払わずに大学病院が人員を確保できる制度なのだと思いました。地域医療枠は「大学に入学したい想い」で応募する人が多い印象なので、義務年限が終わると違う病院に務めるヒトが多く、定着率があまり高い制度ではないと思います。紀平さんの言う通り、病院が直接人員を集めることができれば、そういう制度も利用する必要が無くなり、ゆくゆくは職員全員の待遇も改善されるんだなと理解しました。この講義を聞くまで、「ヒトの紹介 or 人材紹介会社を介さないとなかなか医師の転職はできない」と思っていました。目先の得そうなことにつられず、サービスの得、落とし穴を理解していきたいと思いました。

〈第10回〉これからの病院経営の在り方
「医療戦国時代を生き残れ!!」
〈講師〉石坂 真一郎
石坂さんの話は今まで誰からも聞いたことがないようなジャンルで、とても面白かったです。公認会計士の方のお話も初めてでしたし、医療(介護)を輸出するという発想も目から鱗でした。あとは電車を買ってしまうという話も興味深かったです。オンライン講義なのがもどかしいほどでした。
非常に刺激的で、とても楽しい講義で、あっという間の2時間でした。「石坂さんがいかにして研精会の経営改善を行ったのか?」、具体的な数値やエピソードに基づいたお話をいただき、非常に参考になりました。院長=会長 兼 広報部長、事務長=社長という比喩がこれまでの経験からも非常に腹落ちする表現でした。また、医療分野についてある種冷静なビジネスの視点をお持ちの一方、精神科病院イメージアップキャンペーンなど、情熱を感じる側面もあり、重層的な視点で経営されておられるのだなと感じました。また、病院見学など是非とも行かせて頂けますと幸いです。この度はありがとうございました。
今回の講義を通じて、経営の真髄とはまさに「ヒトを動かすこと」にあると強く実感しました。特に印象的だったのは、経営をスポーツチームの運営や監督の役割に例えられた点です。 研精会が直面した「3つの危機」や組織の硬直化を打破できたのは、単なる制度設計だけでなく、石坂さんが「ヒト」を深く観察し、若手が活躍できる場をつくったり、適材適所の配置を行ったりした結果だと感じました。ヒトをよく観察し、他者に興味を持つ資質こそが、経営において個々の強みを引き出し、組織を活性化させる原動力になるのだと学びました。